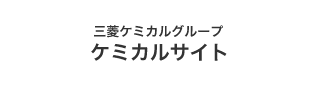ENEOSと三菱ケミカル、プラスチック油化開始に向けたケミカルリサイクル設備の竣工について
2025.08.18
ENEOS 株式会社および三菱ケミカル株式会社が建設を進めていたケミカルリサイクル設備(以下、「本設備」)が、このほど完成し、2025 年 7月 2 日(水)に、三菱ケミカル茨城事業所(茨城県神栖市)において、竣工式が開催されました。本設備は、外部から調達した使用済みプラスチックを英国の Mura Technology 社の超臨界水熱分解技術※によって化学的に分解する油化処理を行います。製造されたリサイクル生成油は、両社の既存設備である石油精製装置およびナフサクラッカーの原料として使用され、石油製品や各種化学品・プラスチックへと再製品化されることにより、サーキュラーエコノミーが実現されます。
当社は、三菱ケミカルグループのエンジニアリング会社として本設備の基本計画段階からこのプロジェクトに参画。三菱ケミカル、ENEOS、海外・国内ベンダー各社と協業し、超臨界水熱分解技術を実プラントへ実装するにあたっての高度な技術的課題を一つ一つ解決しながらエンジニアリング業務を遂行し、この革新的技術に基づく本設備の日本初の建設に大きな役割を果たしました。技術課題に関しては設計、製作、施工、検査、試運転の全域で発生しましたが、ここでは超臨界水加熱器に実施した解決内容を一例として以下に述べます。
- 機器の性能に関して:超臨界水生成には将来的には再生可能エネルギーを使用できるよう、この規模としては世界初となる電気による加熱方式を採用しましたが、臨界点近傍で比重・比熱・熱伝導率が大きく変化するために熱伝達特性が不安定となり、局部加熱による性能低下が発生する可能性があります。そのため詳細の熱流動解析を行い、加熱する機器内で流動の滞留が発生しないような形状を決定し機器設計を行いました。
- 機器の材質、構造に関して:超臨界水を製造する上述の電気加熱器は高温高圧下で稼働するため日本国内の厳重なコード(高圧ガスやボイラー等)要求に合格する必要がありますが、特殊仕様であるため材料、構造、検査方法全てにおいて当局に個別の特例申請を行い、それに合格する必要がありました。当社は、使用状況下における機器の健全性を証明するための詳細な構造解析に基づき、材料、構造、検査方法に関して適切な選定を行い、すべての特例申請に合格させました。
- 機器の製作に関して:電気加熱器の主要パーツには非常に精度の高い穿孔加工が必要でしたが、上述の国内法コードに合格させるために当社が検討した結果、材料は非常に硬度の高い超合金で厚みも大きな部品になり、通常の加工方法では要求精度の実現は困難であることが判明しました。そこで要求精度を実現できる新たな加工方法を検討開発し、機器全体を完成させることができました。
三菱ケミカルグループは「革新的なソリューションで、人、社会、そして地球の心地よさが続いていくKAITEKI の実現をリードする」という Purpose のもと、社会課題に最適なソリューションを提供し続け、素材の力でお客様を感動させる「グリーン・スペシャリティ企業」を目指しています。当社は、三菱ケミカルグループのエンジニアリング会社として、今後もカーボンニュートラル・循環型社会を実現に向けて技術力の更なる向上に努めてまいります。
※ 超臨界状態(高温・高圧)の水を溶媒としてプラスチックの分解を行なう技術であり、分解しながらプラスチックが水に溶解し、この水が生成油の再結合を抑制することで、リサイクル生成油が製造されます。
【竣工式の様子】
 左から 1 人目 石田 進 様 (ご来賓:茨城県神栖市長)
左から 1 人目 石田 進 様 (ご来賓:茨城県神栖市長)
同 2 人目 額賀 福志郎 様 (ご来賓:衆議院議長)
同 3 人目 筑本 学 様(三菱ケミカル株式会社 代表取締役社長)
同 4 人目 山口 敦治 様 (ENEOS 株式会社 代表取締役社長 社長執行役員)
同 5 人目 大井川 和彦 様 (ご来賓:茨城県知事)
同 6 人目 藤井 宏記 (三菱ケミカルエンジニアリング株式会社 代表取締役社長)
【本設備の外観】
 左:プラスチック油化の前処理工程 右:超臨界水熱分解による油化工程
左:プラスチック油化の前処理工程 右:超臨界水熱分解による油化工程
【関連情報】
ENEOSと三菱ケミカル、プラスチック油化の開始に向けてケミカルリサイクル設備を竣工|三菱ケミカルグループ
掲載内容は発表日現在のものです。その後内容が変更になる場合もございますので、あらかじめご了承ください。